【2025年最新】食品衛生とは?
改正法への対応と食品の安全についてわかりやすく簡単に解説(2025年5月27日更新)

食品を扱う事業者にとって、食品衛生は最重要課題です。この記事では、食品衛生の重要性や関連する法律、対策ができない場合のリスク、具体的な対策方法について、2025年の最新情報を交えてわかりやすく解説します。
食品衛生とは
食品衛生とは、食品を衛生的な状態で提供できる環境を保つことを指します。食品衛生の一番の目的は、食品を食べる消費者の健康を守ることです。
食品を扱う事業者は、消費者の生命を維持し健康を支えるために、食品を提供し利益を得ています。提供した食品によって感染症や食中毒を引き起こし、消費者の健康を害してしまうことはあってはならない事態です。
一度、食中毒や異物混入といった問題が発生すると、企業の信頼は失われてしまいます。食品衛生は、食品を扱う事業者にとって最も重要な責務といっても過言ではありません。
食品による危害
食品による健康被害は多岐にわたり、以下のようなものが危害の原因となります。
・食中毒菌・ウイルス:サルモネラ菌、O157など
・化学物質:農薬、添加物など
・経口感染症:コレラ、腸チフスなど
・人獣共通感染症:結核、トキソプラズマ症など
・寄生虫症:アニサキス、トリヒナなど
・混入異物:ガラス片、金属片など
これらの危害を防ぐには、食品衛生管理の徹底が不可欠です。
食品衛生に関連する食品衛生法の特徴
食品衛生に関連する法律の中で、特に重要な食品衛生法について、概要は以下のとおりです。
|
項目 |
内容 |
|
目的 |
食品の安全確保と消費者の健康保護を図ること。食品の衛生管理を通じて食中毒や健康被害を防止する。 |
|
対象 |
食品の製造、加工、販売、輸入に関わる事業者および食品そのもの。飲食店や食品工場も含まれる。 |
|
内容 |
食品の衛生基準の設定、営業許可制度、検査・監視体制の整備、違反時の罰則規定など。 |
|
具体例 |
食品の製造工程での衛生管理基準の遵守、HACCPの導入、営業許可の取得、食品の自主回収義務など。 |
食品衛生法について、さらに詳しく解説します。
目的・内容
食品衛生法の目的は、食品を通じて発生する可能性がある健康被害を未然に防ぎ、消費者の健康を守ることにあります。具体的には、食品の製造や流通過程での衛生管理基準を定め、食中毒などの発生を防止することが中心です。
また、営業許可制度や検査体制を整備し、違反があった場合には適切な措置を講じることで、食品の安全性を確保しています。これにより、消費者が安心して食品を利用できる環境を作り出しています。
対象
食品衛生法の対象品目は、以下のとおりです。
・食品 :医薬品・医薬部外品を除く、ほぼ全ての飲食物
・食品添加物:食品の加工・保存などの目的で使用されるもの
・器具:食品や添加物に直接触れる機械・器具・食器・調理器具など
・容器包装:食品や添加物を入れる・包む箱、袋、包装紙など
・おもちゃ:乳幼児が触れるもの
・洗浄剤:野菜や果実、器具を洗浄するためのもの
「口に触れるもの」全てを対象としているわけではなく、規定された品目に限定されています。
2025年時点での食品衛生法の主な改正内容
食品衛生法は、環境変化や国際化対応のため改正されており、2025年時点での主な改正内容は、以下です。
|
改正項目 |
概要 |
|
大規模又は広域におよぶ「食中毒」への対策強化 |
食中毒発生時の迅速な対応と情報共有体制の整備、広域的な食中毒の拡大防止策を強化。 |
|
「HACCPに沿った衛生管理」の制度化 |
HACCPに基づく衛生管理の義務化により、食品製造・加工の安全性を体系的に確保。 |
|
特定食品による「健康被害情報の届出」義務化 |
健康被害が疑われる特定食品の情報を行政へ速やかに報告することを義務化。 |
|
「食品用器具・容器包装」にポジティブリスト制度導入 |
使用可能な添加物や材料をリスト化し、管理を厳格化。 |
|
「営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」の創設 |
営業許可の要件見直しと新たに営業届出制度を設け、事業者の管理体制を強化。 |
|
食品等の「自主回収(リコール)情報」の行政報告義務化 |
自主回収の実施情報を行政に報告する義務を課し、消費者保護を強化。 |
|
「輸出入」食品の安全証明の充実 |
輸出入食品の安全性確認を徹底し、国際基準に対応した証明体制を整備。 |
各改正内容について、詳しく解説します。
大規模又は広域におよぶ「食中毒」への対策を強化
大規模または広範囲に及ぶ食中毒の発生に対して、迅速かつ効果的に対応する体制が強化されました。この改正は、食品技術の革新に伴い、特定の食品が広域に流通するようになった結果、同一の原因物質による食中毒も広域に拡大するようになったことが経緯となっています。
具体的には、国と都道府県などの連携協力義務の規定が創設されたほか、発生源の早期特定、感染拡大防止措置の徹底が求められる内容に改正されています。
「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」を制度化
食品の製造や加工において、HACCPに基づく衛生管理が法的に義務付けられました。HACCPとは、EU各国や米国など多くの国で採用されている、食品の安全を確保するための衛生管理手法です。
HACCPの導入により、危害要因を科学的に分析し、リスクを管理する仕組みが全国的に標準化され、安全な食品提供が一層確実になります。そのため事業者にとっても、導入することで問題発生によるコストや損失の削減につながるというメリットがあります。
特定の食品による「健康被害情報の届出」を義務化
厚生労働大臣が指定する特定の食品に起因する健康被害が疑われる場合、事業者は速やかに都道府県知事などにその情報を届け出ることが義務付けられました。これは、法律上の根拠を持たず「健康食品」と謳った商品が販売されている実態や、一部の「健康食品」による健康被害が発生していることを受けたものとなっています。
この改正は、被害の早期把握と迅速な対応を可能にし、消費者の安全を確保するためのものです。
「食品用器具・容器包装」にポジティブリスト制度を導入
食品に接触する器具や容器包装の材料について、使用が認められる物質をリスト化するポジティブリスト制度が導入されました。改正前は、使用を制限するネガティブリスト内の物質以外は使用可能でしたが、改正により安全性の高い材料のみが使用されるよう管理が強化されます。
なお、2025年5月末までは経過措置期間となっており、既存の器具や容器包装については一定期間使用が可能です。事業者は、この期間中に新しい制度への対応を進める必要があります。
「営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」の創設
営業許可制度の要件が見直され、より厳格な衛生管理が求められるようになりました。これは、コンビニエンスストアなど、多様な業務形態の事業者の増加を受けた改正です。
また、これまで許可対象外だった業種についても「営業届出制度」が創設され、全ての食品等事業者の所在や業態を把握できる仕組みが整備されました。この改正により、食品等事業者の実態をより正確に把握でき、効果的な監視指導や食中毒発生時の迅速な対応が可能となっています。
食品等の「自主回収(リコール)情報」は行政への報告を義務化
事業者が食品や添加物、器具・容器梱包の自主回収を行う場合、その情報を必ず都道府県知事等に報告することが義務付けられました。届出には、営業者の氏名および住所、自主回収の理由、回収の方法などを明記する必要があります。届出を行わなかった場合や虚偽の届出を行った場合、50万円以下の罰金に処される可能性があります。
この改正は、消費者への迅速な情報提供と安全確保が目的で、回収の透明性と信頼性を高めるためのものです。
「輸出入」食品の安全証明の充実
輸出入される食品については、安全性の証明体制が強化されました。輸入される食肉等については、HACCPに基づく衛生管理が行われている国・地域・施設で製造・加工されたもの以外は輸入してはならないことになりました。
また、乳、乳製品、ふぐ、生食用かきは、輸出国の政府機関発行の衛生証明書を添付したもの以外は、販売用の食品として輸入してはならないとされています。この改正により、国際的な安全基準に適合した食品の流通が促進されています。
食品衛生対策ができていない場合のリスク
食品衛生対策を適切に実施しないことは、事業者にとって致命的なリスクとなります。最も深刻なリスクは食中毒の発生です。食中毒は重症化すると、後遺症が残る疾患に繋がったり、最悪の場合には死亡に至ったりする場合もあります。食中毒は消費者に健康被害を与えるだけではなく、事業所の営業停止や売上低下、賠償責任問題に発展するケースもあります。
食中毒の発生場所として特に多いのが飲食店です。飲食店では料理の提供以外にも、接客サービスや金銭の受け渡しなども行われるため、食品の汚染が起きやすい傾向があります。
一度食中毒を起こしてしまうと、消費者からの信頼を失ってしまいます。食品事業者が事業を継続するには、徹底した食品衛生対策を行うことが重要です。
飲食店の食品衛生対策で注意すべきポイント
飲食店の食品衛生対策で注意すべきポイントを4つ紹介します。これらのポイントを押さえることで、安全で衛生的な食事の提供が可能となり、顧客満足度の向上にも繋がるでしょう。
従業員の衛生状態を保つ

従業員の衛生状態を保つことが、飲食店全体の衛生管理に繋がります。手洗い、日々の健康状態のチェック、清潔な身だしなみの維持を徹底しましょう。特に、お客様に不潔な印象を与えないためにも、清潔な身だしなみを維持することは大切です。もし、従業員の制服を清潔な状態に維持することが難しいという場合は、ユニフォームのレンタルサービスの利用がおすすめです。
ユニフォームのレンタルサービスでは、レンタル会社が定期的なクリーニングと補修を行うため、制服を常に一定の衛生基準で保つことができます。従業員の衛生管理を徹底することで、食中毒リスクを低減し、お客様に安心して料理を楽しんでもらうことが可能になります。
食材を正しく検品する

安全な料理を提供するには、納品された食材の検品を徹底することが重要です。食材の納品時には、鮮度や包装の状態などを細心の注意を払ってチェックしましょう。
また、納品された食材を適切な状態で保管し、使用期限を管理することも重要です。定期的な在庫チェックと先入れ先出しの原則を徹底することで、食材の鮮度を保ち、無駄を減らすことができます。
調理器具の洗浄を徹底する

調理器具の洗浄や消毒が不十分だと、食中毒を引き起こす菌やアレルゲンが他の調理器具に広がってしまう可能性があります。調理器具は使用したらその都度、洗浄・すすぎ・消毒を行うことが大切です。
汚れの落ちやすさは、用いる洗浄用具や洗剤、水の温度によっても変わってきます。従業員には、調理用具の適切な洗浄の仕方など具体的な手順を明示して指導しておくことが大切です。
飲食スペースを衛生に保つ

調理場だけでなく、飲食スペースも衛生的に保つ必要があります。飲食スペースが清潔に保たれているかどうかは、お客様の満足度にも影響します。定期的な清掃と消毒、適切な換気、ゴミの適切な処理が飲食スペースを衛生的に保つための基本です。
また、トイレや洗面所などのサニタリースペースはウイルス感染が起きやすいため、定期的に清掃するようにしましょう。お客様に安心して食事を楽しんでもらうためには、飲食スペースと併せて衛生的に保つことが大切です。
まとめ
食品衛生は、食品を扱う事業者にとって最重要課題です。消費者に安全な食品を提供するためには、法律を遵守し、適切な衛生対策を行うことが大切です。
特に、飲食店では食中毒が発生しやすいため、従業員の衛生管理、食材の検品、調理器具の洗浄、飲食スペースの衛生維持といった食品衛生対策を行うようにしましょう。
消費者の安全を守るためだけでなく、消費者からの信頼を獲得・維持し事業を継続するためにも、食品衛生対策を講じることが大切です。
初版:2024年8月23日
第2版:2025年5月27日
ユニフォームレンタルという選択肢はいかがですか?
お見積り、資料請求はこちらから。




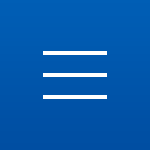








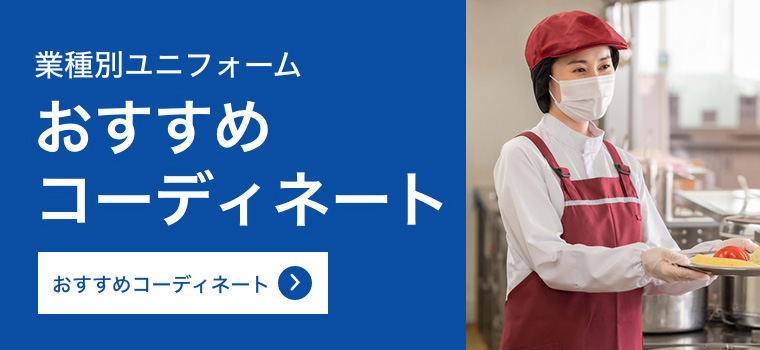







 土・日・祝日を除く10:00~16:00
土・日・祝日を除く10:00~16:00




 土・日・祝日を除く10:00~16:00
土・日・祝日を除く10:00~16:00